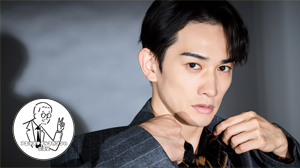「50~60代の方がだまされやすい」傾向も 識者に聞くデマ対策
能登半島を中心とした地震をめぐって、ネット上にデマや真偽不明の情報が相次いでいる。デマや誹謗(ひぼう)中傷問題に詳しい国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)の山口真一准教授に聞いた。
――SNSにデマがあふれています。
2016年の熊本地震でも、ふざけて「ライオンが逃げた」という誤情報を拡散させた人が逮捕された例がありました。今回も、そんな風に偽情報を集めて注目を集めたいといった事例が多いのではないでしょうか。
昨夏から、X(旧ツイッター)では投稿のインプレッション数(視聴されたり表示されたりした回数)に応じて収益が配分されるようになり、人びとの注意を引くことがお金につながる「アテンションエコノミー」が個人レベルで広まっています。これによって、問題が加速しているという印象があります。
――どんな特徴がありますか。
感情を揺さぶられる情報が多く、今回のような災害時に、一般ユーザーがSNSの虚偽情報を素早く見極めるのはとても難しい。ですが、添付された画像を「画像検索」して過去の画像ではないか確かめたり、ほかの人やメディアが「誤情報ではないか」と疑っているかどうかチェックしたりしてほしいと思います。
今回は過去の東日本大震災の画像や映像などが多く流用されていますが、これから1、2年もすると、生成AIで作られた画像を添付した投稿が急増するでしょう。2022年の静岡県の水害でも既に生成AIで作られた偽の被災画像が広まりました。真偽の見極めがさらに難しくなると考えられます。
――ユーザーができることはありませんか。
Xには、誤解を招きそうな投稿にユーザーが補足情報をつける「コミュニティノート」があり、今回、想像以上に機能していると感じました。
誤情報が多い時には、どうし…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【提案】
昨年は関東大震災から100周年の節目で、災害による混乱の中で流言によって朝鮮人虐殺が起こったことについて改めて考えさせられた年でした。今回の能登半島地震をめぐって、まさに100年前と全く同じような流言がSNSで流れているのを見て暗澹たる気持
…続きを読む