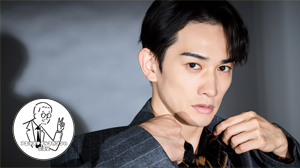希望する働き方、誰が会社と話し合う? 「過半数代表」の見直し提言
労働者一人一人の希望に応じた働き方を実現させるには、会社と労働者が話し合う仕組みの整備が欠かせません。そのために現在、多くの職場で使われているのが「過半数代表」ですが、問題点が指摘されています。厚生労働省が設置した有識者研究会は、法制度を含めた見直しを提言しました。
有識者研究会で最大の焦点
厚労省の「新しい時代の働き方に関する研究会」が10月、報告書をまとめた。最大の焦点は、労働条件を決めるときに労使間の話し合いを反映する仕組みだ。
労働基準法などは最低の労働条件を規制している。ただし、労使が合意することで規制を緩めることができる制度は今もある。
例えば労働時間は、週40時間、1日8時間までというのが労働基準法の原則。労働者の過半数を組織する労働組合か、従業員の過半数に選ばれた「過半数代表者」と労使協定(36〈サブロク〉協定)を結べば、ある程度まで残業させることができる。
労組の推定組織率は約17%。過半数労組がない場合は過半数代表を選ぶことになる。労使の代表者でつくる「労使委員会」が使える労働条件もあるが、導入は進んでいない。
だが、過半数代表の現状には…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら