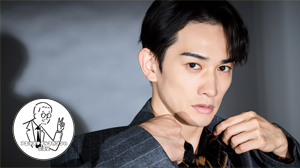第1回大企業と闘った父、自宅に届いた嫌がらせ 息子はそれでも信じ続けた
自宅にかかる無言電話におびえ、懐中電灯を抱いて眠る――。父が水俣病患者だった熊本県水俣市の川本愛一郎さんは、そんな少年時代を過ごしました。「弱い立場で声を上げるのは、ものすごく勇気がいる」と感じたという日々を振り返ります。
「両親を信じて、家族一丸で父を支えた」
私は、水俣病が公式確認された2年後の1958年生まれ。被害が集中した地区の小中学校に通いました。胎児性患者と同世代で、立つとふらふらしたり、ろれつが回らなかったりする子がいました。水俣病の症状はずっとそばにあった。なのに、その話にあえて触れない、ということが子ども心にありました。
祖父は漁師で、水俣湾で釣った魚を父と母、私と妹で食べ、全員が被害を受けています。祖父はけいれん発作など水俣病の症状がそろっていたのに、発症時期が当時の定説から外れているという理由だけで、患者と認定されませんでした。
切ない思い出があります。幼い頃、近所の石垣に座る祖父に小遣いをせびったんですが、「銭がなか」と。私は腹立ち紛れに、祖父の松葉杖を道の中央に置きました。祖父は歩けなくなっていて、取りにいけない。夕方に帰ると、玄関に二つに折れた松葉杖があり、「しまった」と思いました。その夜、父に怒られた記憶はないんです。父も情けなかったんでしょうね。今でも悔やみきれない。私がリハビリ支援の道に進んだ理由の一つです。
父は、祖父が「水俣病ではな…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
「弱い立場で声を上げるのは、ものすごく勇気がいるな、と思いました」。水俣市立水俣病資料館の語り部、川本愛一郎さんがそう感じたのは中学生の時。1971年のことだ。それから半世紀、この社会はどう変わったのか。あるいは、変わらなかったのか。「水俣
…続きを読む