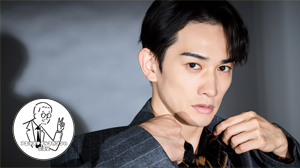児童虐待「過去最多更新」の実態は 見えないこころのケガにも対応を
Re:Ron連載「こころがケガをするということ」第5回
私は精神科医として、日常臨床で、多くの虐待された子どもやその家族、子ども期に虐待を受けて成人期に何らかの不調を抱えている人たちと出会う。最近の10年くらいは、いくつかの児童相談所(児相)の非常勤医師として、あるいは、アドバイザーとしても、児童虐待問題に関わっている。その中で、日本の児童虐待対応は現状のままでよいのか、という思いは年々強くなっている。児童虐待防止に関わるさまざまな立場の人たちは、多かれ少なかれ同じような危機感を抱いていると思う。
今年も9月に、全国232カ所の児相の児童虐待相談対応件数(昨年度の速報値)が発表された。21万9170件と、32年連続で増加、過去最多を更新したらしい。「らしい」としたのは、その数字が実態を表していないからだ。
折しも、今年の8月8日、日本子ども虐待防止学会が、「こども大綱の策定に関する要望書」を内閣総理大臣とこども家庭庁長官宛てに提出した。
そこで、11月に児童虐待防止推進月間を迎えるにあたり、3回にわたり児童虐待によるこころのケガについて考えたい。初回は、要望書でも取り上げられている、「科学的データの把握・公開とEBP(Evidence Based Practice、科学的根拠に基づいた実践)の推進およびEBPM(Evidence Based Policy Making、合理的根拠に基づく政策立案)」の項目に含まれる二つの課題を見てみたい。
一つ目は、日本の統計が、児童虐待の「実態を把握するには有効ではない」という点だ。以下、全国児童相談所長会の「虐待通告の実態調査(通告と児童相談所の対応についての実態調査)報告書」(全児相通関105号別冊)から見てみよう。
児童虐待は、早期発見の必要性から、国民全員に「虐待を受けたと思われる児童を発見した場合」の通告を義務としている(児童虐待防止法第6条)。児相は通告受理後48時間以内に、直接、子どもの安全確認を実施することになっている。安全確認が遅れ、子どもの命が失われるという痛ましい事件が発生したためだ。
この時間制限内の安全確認が、児相業務の大きな負担となっている。にもかかわらず、「通告受理は一元的に管理できておらず、全体を把握して、マネジメントすることが難しい状態にある」という。
その一因は、児相と市区町村の担当課という二つの窓口が並行して通告を受理している点にある。
市民はそれぞれ通告しやすい窓口に知らせると考えられるが、市町村には、児相のように48時間以内の安全確認という規定がない。
その上、「全国の自治体の虐待通告件数のカウント方式や、虐待相談受理の基本ルールが、地域によって様々であり、統一基準での実態把握ができていない」状態にあるとのことだ。
児相においても、安全確認をしたのちに児童虐待ではないと判断されたケースの算定方法が統一されていない。
新たに生じた二重基準
一方、警察庁の方針転換が…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら