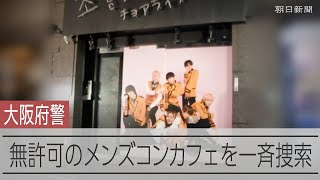「三体」後も続く人気 中国SFはなぜ熱い 成都でヒューゴー賞発表
世界で売れに売れ、日本でもブームを巻き起こした「三体」(劉慈欣著)をはじめ、中国SFは各国で多くのファンを持つようになりました。10月18日から中国では初めてとなる世界SF大会が、「SF都市」といわれる四川省成都で開かれます。
なぜ中国のSFはいま、熱いのか。中国でSFが盛んな理由とは。SF界のノーベル賞とも呼ばれる「ヒューゴー賞」が発表されるこの一大イベントを前に、「三体」の邦訳の監修も務めた作家の立原透耶さんに中国SFについて語ってもらいました。
立原透耶さん
たちはら・とうや 1969年生まれ。作家、翻訳家。著作に「凪(なぎ)の大祭」など。中国SFの翻訳も手がけ、2021年に「中華圏SF作品の翻訳・紹介の業績」によって日本SF大賞特別賞を受賞した。大学生の時に手に取った「SFマガジン」で中国SFの存在を知り、のめりこんでいったという。
――まもなく世界SF大会が成都で開幕します。
世界SF大会がアジアで開かれるのは、2007年の横浜に次いで2回目です。欧米との政治体制の違いを乗り越えて、人々がSFを通してつながる意味があります。
「三体」も中国系アメリカ人作家、ケン・リュウの翻訳による英語版が2014年に出たあと、翌年にヒューゴー賞を受賞し、世界的な人気を得るに至りました。
中国内陸部にあり、三国時代の蜀(しょく)の都だった成都はいま、中国SFの聖地のような場所になっていて、「SF都市」として自らを売り出しています。「三体」が連載されたSF雑誌「科幻世界」の編集部も成都にあります。
――中国SFはそんなにおもしろいのですか。
米国や日本でかつてSFの黄金期があったように、いま中国はSFの黄金期だと私は考えています。「三体」を書いた劉慈欣は、「日本沈没」などで知られる小松左京のような存在だと言っていいベテランで、中堅、若手も育っている。個々の作品だけでなく、中国SF全体の勢いにも魅力があります。
若い作家たちは始めから海外の市場を視野に入れて書いているように見えます。作品から中国らしさ、中国の要素を抜いても成り立つ、普遍性のある作品になっています。
「中国らしさ」の扱いに変化
――英語に翻訳され、英語圏で人気が出たのですね。
かつては英語圏で読まれる作品には、「中国らしさ」やエキゾチシズムが求められていたと思います。中国的な要素がなければ、あまり受けないという側面がありました。
中国らしさとは、まずは情、ウェットな味付けですね。そして、中国の文化が出てくる作品が好まれました。古代を舞台にするものもあるし、中国の現代社会を描いているものもあります。
しかしその傾向も、この1、2年で変わってきました。いかにも中国的でなくても、いい作品であれば英訳されるようになった。それだけ中国SFが英語圏にも浸透したということです。
――なぜ中国ではSFが盛んなのでしょう。
中国は国を挙げてSFを教育…