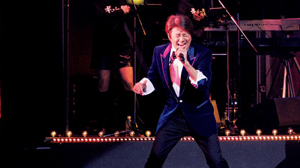療育も仕事も、親が両立できる社会に 難病の娘持つ男性が施設つくる
サラリーマンだった森康行さん(33)は、幼い娘が難病だと分かって会社を辞め、岐阜県岐南町で重度障害児のための通所施設を始めた。「自分たちができなかったことをほかの人が実現できるように、選択肢を増やしたい」。施設の名前にはそんな願いを込めた。
第3の選択肢を意味する「サードストリート」は、住宅街にある。昨春に民家を改修してオープンした。重度障害児らを対象に、放課後等デイサービスや、児童発達支援のサービスを提供する。定員は5人で、3歳から小学生までが毎日3~5人ずつ通ってくる。
1階の日当たりの良いフロアにはクッションマットが敷かれている。ここが療育ルームで、看護師や保育士が付き添う。芋掘りなどの行事のほか、アロマをたいたり入浴剤を入れて足湯をしたりと、施設では五感を使った活動に力を入れる。
利用は午前10時から午後5時まで。仕事との両立に悩んだ経験から、「午後5時まで」にこだわった。
次女おとちゃん(5)も施設を利用する一人。2歳のころ難病「レット症候群」と診断された。ほとんど女児だけに発症し、運動機能や言語能力が次第に衰えていく神経疾患だ。
「できていたことがどんどんできなくなる病気。診断が出たとき、寿命はどうなるのか一番気になりました」。そのころを思い出すと、森さんは涙で言葉が詰まってしまう。
おとちゃんが通っていた岐阜市の保育園は診断後も1年余りは受け入れてくれた。だが、年度替わりのタイミングで退園することに。そのとき3歳。「周りの子が『おとちゃん』と声をかけて近づいてくれると、おとも笑顔になる。楽しいとか、うれしいとか感じながら内面が成長していた」と感じていた。
当時、森さんは部下十数人を抱える企業の管理職。週1回のリハビリや通院に付き添う間は部下からの電話に出られず、もどかしさが募った。
自宅近くで通えそうな施設を探したものの、重度障害児を受け入れる施設はどこも利用時間が短かった。仕事と何とか両立できそうな午後5時までの施設は、ついに探せなかった。
「世間から突き放された感じというか、人生がどん底のように感じて、本当に真っ暗でした」
共働きの妻は、仕事にやりがいを感じていた。「男女関係なく、子どもに障害があるから夢のある仕事を辞めなければいけないのは違う」。それなら、自分が会社を辞めて施設をつくろうと決めた。
立ち上げた後、障害児が生まれたばかりだという親から相談の電話があった。「子どもを(自分では育てずに)手放そうと思っている」。切羽詰まった声で、そう告げられたのが印象に残ったという。
目下の課題は、利用者を増やして経営を安定させること。通所サービスに対して自治体から支払われる給付費は日額で決まり、利用時間を長くした分への加算はない。「今の仕組みだけでは、親として理想の施設をめざすのは難しい」
施設経営に苦労はあるものの、目指す社会像ははっきり見えている。「子どもが生まれた瞬間は最高の喜び。障害があっても当たり前に生きられて、その誕生を喜べる社会にしたい」