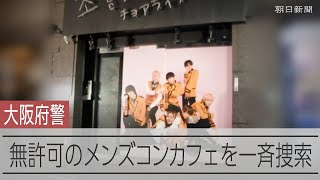ウィキペディアで町おこし、ご当地ネタをネット発信 各地で取り組み
誰でも書き込みができるインターネット上の巨大な百科事典「ウィキペディア」に、隠れた観光名所などを紹介するページを作ることで、町おこしにつなげようとする取り組み「ウィキペディアタウン」が全国で広がっている。各地の図書館や資料館などが市民に参加を呼びかけ、書き込みを充実させることで、地域の魅力を発信する試みだ。
10月1日には福井県美浜町で「ウィキペディアタウン in 美浜」があった。町立図書館の司書や市民に交じって記者も参加。戦国時代に城下町として築かれた町内の佐柿(さがき)集落に焦点を当て、下調べに取りかかった。
午前中は地元資料館の館長と、木の葉が色づき始めた集落を散策。織田信長が越前を攻めた際に使ったと伝わる山城「国吉城」や、藩主が植えたとされる町指定天然記念物の大イチョウの由来などを学んだ。
午後には図書館に戻り、ページの編集作業に詳しい「ウィキペディアン」と呼ばれる講師の手ほどきを受けて「佐柿」のページを新設。集落の地理や名所などを分担して書き込んだ。
記者は名所のうち、江戸幕府の決めごとを掲げていた集落中心部の「高札場」や、弘化3(1846)年の銘がある鬼瓦が残る町屋「小畑家住宅」の項目を担当した。
その際、頼りになったのは図書館にある文献だ。郷土の歴史をまとめた福井県史や美浜町教育委員会の冊子などを照らし合わせ、引用した。引用元を脚注で明示し、閲覧者が情報の確からしさを検証できるようにした。こうした心がけによって臆測や恣意(しい)的な記述を排し、情報の信用性を高めようと申し合わせた。
この「佐柿」のページは、大量の閲覧が期待できるウィキペディア日本語版のトップページで「新しい記事」の代表に選ばれ、紹介された。
ウィキペディアタウンは20…