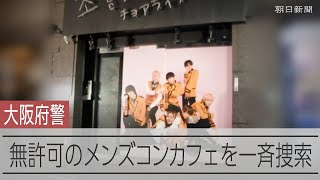「#保育園に入りたい」は終わってない 待機児童問題の先にあるもの
保育園の入園システムは、「子どもの育ち」を支える視点が足りないのではないか――。
子育てしやすい社会の実現などを求めて活動する市民団体「みらい子育て全国ネットワーク」代表の天野妙さんは、保育園を巡る課題をこう指摘します。今春の待機児童が3千人を切り、過去最少となったものの、保護者からは保育を巡る要望や不満の声などが上がっています。待機児童問題の先の課題はなにか、天野さんに聞きました。
「保育園落ちた」がきっかけに
――2017年に、現在の全国ネットワークの前身となる団体「希望するみんなが保育園に入れる社会をめざす会」を設立されました。
16年に「保育園落ちた日本死ね!!!」と訴える匿名のブログが話題になったことがきっかけです。
私も3人の子どもがおり、特に中学2年生になった長女が待機児童になったとき、絶望感、焦燥感、さまざまな思いを持ちました。その経験があり、ブログにつづられた思いに共感したのです。
周りにも、保育園に入るための「保活」に悩む保護者たちはたくさんいました。
「保育園を増やしてほしい」「保育園に入れなくて、仕事を続けられないかも」……。こうした思いを、幾度となく耳にしました。この怒りや不安を、「過ぎればいい」として片付けるのではなく、なんとか社会の問題として政府まで届けられないだろうか。そして、私たちの世代で待機児童問題を解決できないか。そんな思いで、保活を経験した保護者たちと一緒に、団体を立ち上げました。
SNSでの発信や、国会議員を巻き込んだシンポジウムを行いました。
1600万回も…
――「#保育園に入りたい」と、ツイッターで発信した狙いは。
保護者の声を可視化しようと考えました。2017年、4月入園の申し込みに対する結果通知が自治体から届く年明けごろから、「#保育園に入りたい」というハッシュタグを作り、保育園に落ちたことを知らせる「保留通知」をツイッターに投稿してもらうよう呼びかけました。
これには、大きな反響がありました。ツイッター上には膨大な数の保留通知の写真が集まりました。一連の投稿がツイッターに表示された回数は、1600万回以上にもなります。
自治体の中には、「保留通知」を受けた保育園に入れない子どもでも、「待機児童」には数えない運用をしているところもあります。「保育園に入れないのに、なかったことにされてしまう」。そんな理不尽さや怒りも、この動きを後押ししたと思います。
待機児童ゼロだけではなく、団体名に「希望するみんなが保育園に入れる」という言葉を入れたのにも、こうした背景がありました。
――待機児童はずいぶん減ってきましたが、現状をどう見ていますか。
当時は、「仕事をやめなくてはいけないかも」「どこにも行くところがない」。そんな声が目立っていました。
確かに、それに比べれば「どこにも入れない」という状況は改善されつつあると感じます。でも、「この園がいい」「この時期に入りたい」といった個別の希望には、まだ対応しきれていません。それでいいのでしょうか。
「どんな園でも、入れればラッキー」と考えざるを得ない段階であることも、本当はおかしいと感じます。
「入れない」理不尽さ、怒っていい
――自治体が入園申し込みを受け付け、保護者の就労や家庭の状況などに応じて点数を付けて入園の優先順位を決めていく認可保育園のシステムでは、「4月入園」以外の選択肢が難しい、という声も聞きますね。
本来、保育園は「必要とする人」が希望するタイミングで利用できるようにすることが求められています。待機児童数が減ったのは、保護者が空き枠を調べ、入園確率の高い選択ができるよう、育休期間や生活を組み立てている面もあるのではないでしょうか。
私自身も、保育園に入れないと知って、自己責任でなんとかしなくてはと思っていたことがありましたが、本当は、職場復帰したい時期に必要な保育が受けられないことにもっと怒っていいと思います。
保育園、どんな親子も受け入れて
――フルタイム就労でないと入りづらいという状況も残されています。
就労の形態・時間も入園審査…