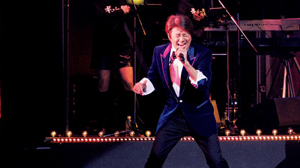保育園の外遊び、3割の自治体が一定の暑さで中止 東京23区など
夏の暑さが増す中、子どもが熱中症にならないよう外遊びやプール遊びを控える動きが保育の現場で広がっている。朝日新聞が自治体にアンケートしたところ、政令指定市と東京23区のうち、約3割が独自の基準を設け、一定以上の暑さで、公立保育園などの屋外活動を中止していた。
気象庁によると最高気温が35度以上になる猛暑日は1990年代半ば以降、全国で大きく増えている。東京都心では今月3日まで9日連続を記録し、過去最長となった。
熱中症の救急搬送者数や死亡者数は増加傾向にある。「災害級」と言われた2018年の猛暑では、死者が1500人を超えた。気候変動などで今後も災害級の暑さが懸念されるとして、国は21年度から「熱中症警戒アラート」の運用を全国で始めた。体が小さく、体温調節が未熟な子どもは特に注意が必要だ。
アンケートは6月下旬に実施。20の指定市と東京23区とともに、00年以降の8月の歴代最高気温の上位自治体の保育園の担当課にも尋ね、51自治体すべてから回答を得た。
多くの自治体が参考にするのは熱中症の危険度の指標「暑さ指数」だ。気温のほか湿度や日射・地面からの照り返しなどから算出する。
値が28を超えると熱中症の搬送者数が増加する。日本スポーツ協会の熱中症予防の運動指針では、28以上で「激しい運動は中止」、31以上で「運動は原則中止」としている。33以上が予測される日に、国のアラートが出る。
アンケートでは、横浜市や埼玉県熊谷市など15自治体が、暑さ指数や気温に基準を設け、基準以上の場合、公立園などで外遊びやプール遊びを原則中止していた。全体の4割以上の自治体が、公立園などに「暑さ指数計」を配備していた。気温や湿度などを測って指数を算定し、基準を超えるとアラームが鳴るように設定できる。
こうした取り組みが始まったのは、ほとんどが「災害級の猛暑」だった18年以降だった。
地球温暖化もあり、日本の平均気温は100年あたり1・28度の割合で上がっている。ここ数年は加速し、歴代年平均気温トップ3は19年以降の年が占める。
全国の小中学校・高校などの設置者には、国が21年に保健室の備品として暑さ指数計を配備するよう通知を出した。また熱中症対策のガイドライン作成の手引もまとめている。
市からメール「暑さ指数31以上の見込み」
保育の現場では、熱中症予防…