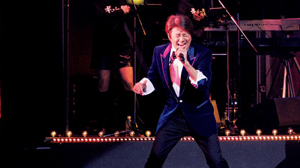第101回その時ブチャで何が ロシア兵も恐れない母、電話で泣き続けた3分間
国際社会では「ブチャ後」との言葉が使われ始めています。ロシア軍の侵攻後、ウクライナの首都キーウ(キエフ)近郊のブチャで起きた虐殺は、それほどの衝撃をもって受け止められました。無抵抗の市民を殺しただけでなく、拷問を加え、処刑し、遺体を放置したり損傷したりしたその残虐さが、人命尊重を基調としてきた現代欧州の価値観を揺るがすものだったからです。
では、実際にどんな出来事が起きたのでしょうか。通り沿いの5軒に残った11人全員が殺害されたイワナフランカ地区を訪ね、その実態を探りました。
ウクライナでの取材経験が豊富な国末憲人・ヨーロッパ総局長。住民たちを訪ね歩くうち、ある部隊の存在に突き当たります。後半でその正体に迫ります。
ウクライナの首都キーウ(キエフ)北西郊ブチャに暮らすタチアナ・ナウモワ(38)は、母から受けた最後の電話の様子を、鮮明に記憶していた。
元ガス会社員の父セルゲイ・シドレンコ(65)は、ウクライナ民主化運動の熱心な活動家だった。親ロシア派政権の不正を市民が追及した2004年のオレンジ革命や、親ロ派政権が倒れた14年のマイダン革命で、抗議の先頭に立った。
母リダ(62)は楽天家で世話好き。近所の独り暮らしのお年寄りらに、しばしば料理を配っていた。
今年2月27日、ロシア軍がブチャを占領すると、一家が暮らすイワナフランカ地区にも装甲車両が駐留した。
リダは恐れず、ロシア兵に「なぜ来たのか」「いつまでいるつもりか」などと母語のウクライナ語で問いただした。ロシア語で答える兵士との会話はかみ合わなかったという。
ブチャを占拠したロシア軍側と、川を隔てた隣町イルピンを死守するウクライナ軍との間で、砲撃戦が激化していた。
砲弾の中を逃げるか、とどまって戦闘の収束を待つか。一家の判断は揺れた。
自宅は3月3日に停電し、5日にはガスも止まった。3月のウクライナは零下になり、凍える寒さだ。タチアナはこの日、夫や息子とキーウに脱出。12日には同居の兄も自宅を離れた。父母だけがとどまる選択をした。
【プレミアムA】「死の通り」 ブチャ 生存者の証言
大量虐殺の悲劇に見舞われた街ブチャに「死の通り」と呼ばれる場所があります。生存者が語るロシア占領下の「絶望の1カ月」とは。金成隆一記者が住民の証言を丹念に集めました。臨場感のある写真や映像とともに伝えます。
「殺しはしないと、信じていた」
「ロシア軍でも、対話をすれば殺しはしないと、両親は信じていました。体の不自由な隣家のおばあさんを1人にさせられないとも考えていた。それに、6匹のネコの世話もあったし」
12日前後、ロシア軍の部隊が交代した。次に来たのは尊大で粗暴な部隊だったと、住民たちは証言する。
この地方の民家には、食料を備蓄する地下蔵が備わる。父母は砲撃を避けて地下蔵で暮らし、3日に1度は外に出てタチアナに携帯で連絡を取った。
ロシア軍の電波妨害のせいか、携帯は普段通じなかったが、家の一角だけに通じる場所があった。通話は1回約20秒。母は「大丈夫」と気強く、近所の人々の様子を伝えていたが、次第に「寒い」「腹が減った」と漏らすようになった。
最後の電話は3月22日。涙…
- 【視点】
今日のような日だからこそ、いつもは同じ人間と思えないようなその残虐さに目を背けたくなったり、自分たちの世界との遠い距離を感じる内容も、どこかで繋がりを感じ、直視できる気がする。一人一人の人間の尊い命の大きさは、どれも同じだ。日本の日常ではあ
…続きを読む