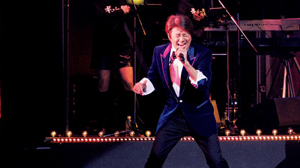第11回働き方改革の担い手側に聞いてみた 若手の「違和感」届いてますか?
働き方改革への嘆きの声が、働く20代に広がっている。
「仕事量は変わらないのに残業は制限され、結局はサービス残業」「働きたいときに働けない」「育休取得で職場にしわ寄せ」。元はといえば、長時間労働の見直しから始まった改革は、恩恵よりひずみが目立ち、何のための改革か納得できないまま、制度と実情のギャップが広がる。
何をめざし、何のための改革なのか。街頭で聞いた働く20代の声を胸に、働き方改革を担う側を訪ねた。
働く20代の「本音」求めて全国6都市へ
会社に入って数年、仕事に慣れ、楽しみも難しさも分かり始めるのが20代中盤です。それゆえに働く意味を考え、将来をどう描くかを悩み始める時期でもあります。生き方の選択肢が無数にあるからこそ、迷いは尽きません。「ワーク・ライフ・バランスを」と言われてもモヤモヤするばかりの24~26歳の記者6人が、突破口となるヒントを求めて3月下旬、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡に向かいました。「働く20代」への聞き取りアンケートから見えた、この世代の実像や本音をお伝えします。働き方や価値観の違いにギャップを感じる上の世代に向けて、識者の解説や分析をインタビューでお伝えします。
5月中旬の平日、東京ビッグサイトで「働き方改革EXPO」が開かれると知り、取材に向かった。展示棟の一つは、企業の人事や総務部門の関係者らでにぎわっていた。目的の場所にたどり着くと、業務効率化のためのツールや、最新鋭のオフィスを紹介するブースが所狭しと並んでいた。
「コロナ禍でウェブ会議がどんどん入り、若手社員の議事録作成が負担になっている。本来、文字起こしは時間をかけてやる業務ではない」
AI(人工知能)が音声を自動認識して話し声を文字化するアプリを開発したアドバンスト・メディア(東京都豊島区)の社員が、実演付きで熱弁してくれた。事前に設定すれば、発言者やキーワードを識別する機能も付く。3月末時点で600近い民間企業・団体のほか、500以上の省庁・地方自治体で導入されているという。
改革の熱上がる企業、若手とのずれはどこに?
「寝ろ。」。壁に書かれた大きな文字にひかれてブースをのぞくと、手書きのイメージを送れば、寝ている間に海外在住の委託スタッフがプレゼン資料に仕上げるサービスをアピールしていた。昨年創業したTimewitch(東京都渋谷区)のブースには「帰らない部下 俺のせい?」「在宅勤務という名の24時間勤務」など、若手主体の社員が自作したフレーズが掲げられ、思わず「うんうん」とうなずいてしまった。
主催者によると、総務・経理、広報など向けの展示会と合わせて460社がブースを構え、イベントがあった3日間で約3万2千人が訪れた。働き方改革を技術面で支援する製品を売りたい企業と、その導入を検討する企業が商談を繰り返していた。
改革に熱を上げる背景には、若手の働きやすさを進めようとする企業側の危機意識があると感じた。だが、3月下旬の街頭アンケートでは、改革を進める側と受け入れる側のギャップを強く感じた。そのずれはどこにあるのだろうか。
東京で出会ったテレビ制作会…