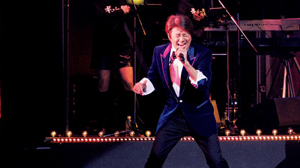不採算の鉄道、「コスト」以外の議論も必要 関西大の宇都宮浄人教授
JR西日本が、採算がとれないローカル線の収支を初めて公表した。1キロあたりの1日平均利用者数を表す「輸送密度」が2千人未満の路線だ。苦しい経営状況を自治体や沿線住民に知ってもらい、廃線も含めた議論を深めるねらいがある。人口減が続くなか、鉄道はどうあるべきか。関西大学の宇都宮浄人教授(交通経済学)に聞いた。
――JR西日本は1キロあたりの1日平均利用者数が2千人未満の路線のあり方を議論したい考えです。
「2千人という数字が独り歩きして、それ未満になればダメだという世論が醸成されるのは危険です。輸送密度が2千人未満でも、ピーク時には学生らがぎゅうぎゅう詰めで乗っていることもあります。『大量輸送』と『時間の正確性』という鉄道の特性が生かせないわけではありません」
「バスや自家用車で代替すれば良いという意見もありますが、鉄道と比べれば輸送力が劣ります。例えば300人を運ぶ場合、バスは何台も必要でしょう。バスは渋滞に巻き込まれれば、目的地にも遅れます。バスを信頼できなくてみんなが自家用車に乗り始めると、もっと渋滞します。『脱炭素社会』ともかけ離れていると思います」
――とはいえ、収益を見込めない路線もあります。
「たしかに、輸送密度が2千…