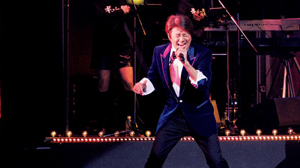見過ごされた基準3倍超の盛り土 経緯も責任もあいまい
静岡県熱海市で起きた土石流の起点付近にあった盛り土は、県条例による基準の3倍を超える高さまで積まれていた。土の総量も届け出よりはるかに多かったとみられている。災害リスクが高い状態はなぜ見過ごされてきたのか。全国に危険な盛り土はどれくらいあるのか。国の対策づくりも始まったばかりだ。
「盛り土が崩れ去り、被害を甚大にした。そのために122戸もの住居が被害を被った。44戸は濁流にのみ込まれた」
静岡県の川勝平太知事は9日夕、土石流発生から1週間となるのを前に記者会見を開き、被害状況をこう総括した。
県によると、盛り土は標高350~400メートルにわたって造成され、高さは約50メートルだったとみられる。土砂の崩壊などを防ぐことが目的の県条例に基づく基準は、盛り土の高さを「原則15メートル以内」と定めており、3倍を超えていた計算だ。
土地を所有していた神奈川県小田原市の不動産会社が2007年に熱海市に届け出た計画では、盛り土の高さは標高365~380メートル付近の15メートル、土の量は約3万6千立方メートルとされていたが、実際には約5万4千立方メートルあったと推定されている。
難波喬司副知事は7日の記者会見で「排水溝と堰堤(えんてい)を入れる計画が届け出られているが、それは高さ15メートルを支えるもので50メートルには耐えられない」と発言。工法が不適切だったとの認識を示した。雨水がたまらないようにする排水装置など、崩落を防ぐための設備が適切に設置されていなかった可能性も指摘されている。
県は、崩落した土砂は約5万5500立方メートルで、ほとんどが盛り土だった可能性があるとみている。ただ、盛り土がいつから基準を超える状態だったのかは不明のままだ。県は、10年以降の造成の経緯や行政の対応については現時点でわかっていないとして、落ち度がなかったかなども含め、引き続き調べるとしている。
土地所有者が変更、不透明な誰がいつ
ルールを大幅に超える高さの盛り土は、いつ、誰が造成したのか。
県などによると、現場はもと…