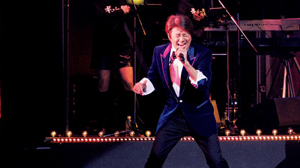盲ろう者通訳・介助、修業終えた記者は誓った
盲ろう者の意思疎通と外出介助を担う通訳・介助員を志し、記者も挑んだ2年の修業が終わった。これで「プロ登録」が可能になる。「今日は終わりではなく始まり」。3月にあった養成講座2年目コースの修了式の日、講師の言葉がずしりと響いた。
2年目コースは昨秋から岡山県津山市で8回開かれた。記者の私を含む9人が「完走」した。最終日の講義は「通訳・介助員の業務」について。通訳・介助員の養成と派遣は障害者総合支援法に基づく都道府県の必須事業となっている。講座を終えた受講生は「盲ろう者向け通訳・介助員」として県に登録できる。
登録の方法、盲ろう者の利用申し込みから現場派遣までの流れなどの説明を聞くうち、これまでの講座の苦い経験が脳裏をよぎった。「最終試験」の外出介助でやらかした失敗の数々。通訳中に頭が真っ白になり、固まってしまったこと――。
そこへ講師の声。「移動介助は、基本一人で担当します」。思わず「無理」とつぶやいていた。
講師の言葉は続く。「たった2年ですべて出来るようになる人はいません。今日は終わりではなく、始まり。苦手から逃げず、経験から学び続けて下さい」
養成講座が始まった2年前、受講生は14人いた。新型コロナの感染が広がったのは1年ほどたってから。盲ろう者との意思疎通は、接触が避けられない。検温や消毒、換気、県外講師の招請中止など最大限の対策を講じて、2年目コースは3カ月遅れでなんとか開講された。しかし普段は介護現場で働く受講生らが継続を断念し、ゴールできたのは9人だけだった。
一人ずつ、岡山盲ろう者友の会の青江英子会長から修了証を受け取った。青江さんは手話で「コロナに負けず、よく頑張ってくれました。これからは通訳・介助員として私たちを支えて下さい」とあいさつ。手の中のA4サイズの修了証が、重かった。
◇
「見えず聞こえない世界」はどんな風景だろうか。そんな好奇心から2年前、受講を決めた。私の感じたことを伝えようと、今回を含めて計14回、記事を書いた。
「暗く寂しい世界だろう」という先入観は正直あった。だが、講師を務めてくれた盲ろう者たちから、手のひら越しに伝わる言葉は温かく豊か。みんな朗らかで楽しい人だった。
しかし、見えて聞こえる世界との落差は大きい。盲ろう者は新型コロナの情報が入らないと不安を口にした。施設で暮らす人の中には感染の広がりすら分からず「だれも会いに来ない。なぜだ!」と怒る人もいたそうだ。
そんな彼らに情報を伝え、外出の機会を支えるのが通訳・介助員だ。だがそれだけの存在でいいのか。
実習で目と耳を塞いで歩くと、普段は気付かない「バリアー」をいくつも実感した。歩道の多くは狭く、でこぼこや傾斜が足元を脅かす。白杖(はくじょう)を見ても減速しない車の運転手。間隔が短くて渡りきれない信号。路線バスの乗降口は狭く、段差が大きい。量販店の通路には商品を盛った箱がはみ出ている。速度が速いエスカレーターは恐ろしい。
なのに、彼らを支える福祉機器はあまりに少ない。聞こえない人には光で知らせる機器が、見えない人には音声で支える機器がそれぞれある。だが、どちらも使えない盲ろう者が活用出来る機器はほとんどない。
安全に歩ける生活環境になれば、盲ろう者の世界は広がる。触覚や嗅覚(きゅうかく)を活用した機器の開発が進めば、自分でできることが増える。人生100年時代を迎え、生涯の途中で思いがけず視力・聴力を失う人は増えるだろう。盲ろう者が生きやすい社会は、間違いなく誰もが生きやすい。
お店の人やバスの運転手さんら出合った一人一人は親切だった。でも、個人の善意に頼るだけでは限界がある。見えて聞こえる人には感じにくいバリアーは、当事者が自ら指摘しないと、社会は変わらない。私も実習するまで、分からなかった。発信する勇気を後押しし、手のひらで受けとめた言葉を声や文字に変換し、届ける。そういう社会との架け橋となることが、通訳・介助員の大事な役割だろう。一人の記者として、人間として、そういう存在になれればと思う。
◇
今年度の養成講座は7月から倉敷市で開講予定。定員10人。詳細など問い合わせは岡山盲ろう者友の会事務局(電話兼ファクス086・227・5004)へ…