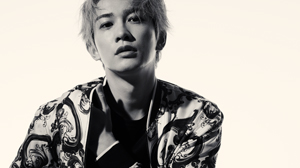視覚障害者を助ける眼鏡 北九州市で実証実験
【福岡】目が不自由な人が駅のホームで安全に歩くのを支援する「眼鏡」を、九州工業大出身の起業家が開発し、北九州市で実証実験した。開発者が取り組んだ背景には、事故で体が不自由になった母への思いがある。
平日の正午前、筑豊電鉄黒崎駅前駅(北九州市八幡西区)のホーム。小型カメラ付きの眼鏡をかけた男性がホームの端に近付くと、男性が持つ白杖(はくじょう)が震え、歩みを止めた。
男性が身につけていたのは、福祉機器の開発を手がける「マリス creative design」(東京都)が商品化を進める装置「seeker(シーカー)」。小型カメラが点字ブロックの位置を捕捉し、演算装置でホームの端までの距離を計算。端まで1・5~2メートルの範囲に近付くと白杖に取り付けた振動機が作動する仕組みだ。
ホームでは車両や構内放送などの音がするため、音ではなく振動で危険を知らせる。実証実験に協力したNPO「北九州市視覚障害者自立推進協会あいず」の事務局長、高清秀さん(60)は自身も視覚障害があり、「多様な音が入り交じる駅の構内では、方向感覚や自分の位置を見失うことも多い」と話す。別のホームに入ってきた電車の音でも自分が乗る電車だと勘違いすることがあるといい、シーカーが実用化されれば「安心感が増すと思う」。
マリス社の社長和田康宏さん(44)は「どのような振動が危険を知らせるのに最適か。障害者の意見を聞いて改良していきたい」と話す。
今は眼鏡に小型カメラだけが装着され、演算装置やバッテリーは別。今後、すべてを一体化した商品を目指す。軽量化や、演算装置が出す熱の処理など課題は多い。通信機能を持たせて演算を遠隔のクラウドコンピューターに任せれば解消するが、震災発生時などで通信用電波が途切れたときに装置が働かなくなる。最も必要とされる非常時に使えるようにと、単体で機能する装置にこだわる。装着した人が格好良く見えて、外出が楽しみになるようにと、デザイナーの手を借りておしゃれな完成品にしたいという。
和田さんが3歳の時、母が事故で脊椎(せきつい)を損傷して歩くのが不自由になった。子どもの頃、母と一緒に出かけると「自分だけでは支えきれず、誰かに助けてもらわないといけなくなるのでは」と心細くなった。一方で、「大丈夫かな。助けた方がいいかな」と、様子をうかがう周囲からの視線を重たく感じた。
障害者がもっと自由に出歩けて、社会に溶け込む支えになるような機器を作りたい。そう志し、九工大の福祉工学などを専門にする研究室で学び、大手メーカーでものづくりの腕を磨いた。カメラのレンズ制御の開発などを手がけた後、2018年に独立した。
「ホームからの転落事故を防いでほしい」という視覚障害者の声に触れ、シーカーの開発に着手。東京都や北九州市のベンチャー支援事業に採択された。完成品を今夏開催予定の東京五輪・パラリンピックで視覚障害者のボランティアに貸し出せないか検討中だ。
和田さんは「日本の福祉機器開発は高齢者介護向けが中心。障害者支援の機器開発で新たな産業を生み出したい」と力を込めた。