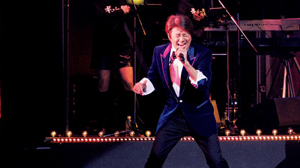大人が黙るサッカー大会 密着して見えた小学生の成長
考えさせて伸ばすには?
パッと見は通常の少年サッカーの試合だ。だが、しばらく見ていれば、あることを感じ取る。
そう、あの小うるさく、時に威圧的な大人の声が一切ないことに。
ベンチにコーチの姿はない。聞こえるのは、子どもたち同士の指示と得点時の歓喜の声だけ。
1月16、17日、愛知県岡崎市で開かれた小学4年生の大会。県内の地域クラブ10チームが参加した。指導者や保護者は一切、口出ししない。
名付けて、サイレントリーグ。
子どもたちだけでつくる大会だ。スポーツの場で、大人が当たり前のようにしてきたことへのアンチテーゼがこもっている。
いくつかの約束がある。
●メンバー決定、戦術、ウォーミングアップなど試合に関わる全てのことを子どもたちに委ねる
●試合の間、子どもがいるエリアに大人は入れない
●行き帰りの道中も、大人は「言いたい一言」を我慢する
さて、子どもの主体性を大事にするといっても、本当に子どもたちだけでできるのだろうか。初参加クラブの一つ、碧南市の碧南FCに2日間密着し、変化を追ってみよう。
連載「子どもとスポーツ」
子どものスポーツの現状を掘り下げる連載の第2シリーズです。テーマは「主体性」。子どもたちだけで考えて臨んだ大会で得られた成果は何だったのでしょうか。記事の後半で紹介します。
会場入りすると、地面にブルーシートを敷いて荷物を広げ、どこかハイキング気分。ウォーミングアップの開始は遅れ、10分しか体を動かせずに第1試合を迎えた。キックオフ時には選手が1人足りず、ピッチから名前を呼ばれた子が慌てて入っていった。
本当に、大丈夫?
それでも、この第1戦は3―1で勝利した。
「案外、黙っていてもできるんだなあ。ポジショニングのコーチング(互いの声かけ)も子どもたち同士でやっていた」
杉浦元コーチと金城レイナルドコーチは驚きを隠さなかった。子どもたちはベンチでストップウォッチを見ながら、選手交代も自分たちでこなした。
金城コーチはブラジル出身の日系3世。12歳で来日するまでブラジルのクラブでプレーしていた。南米のコーチは口うるさくないのか聞くと、「チームによりますね」。
「プレーがダメだと試合から外し、はい上がってこいという態度をとる。厳しさの種類が違います」
幸先良いスタートを切ったチームは次の試合まで約2時間。主将が「おにぎりを1個だけ食べていいよ」と指示をしていた。
【第2戦 3―7で負け】
強豪・愛知FCとの対戦。実はこれが、子どもたちが雪辱への戦略を考え、ほろ苦さを味わう物語の始まりだった。
前半は3―1とリードした…