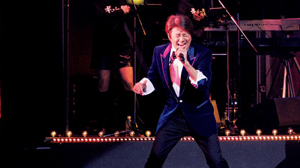逼迫した現場に危機感 釜萢氏「病床確保、今後も課題」
病院のベッドが空いてもすぐに埋まり、待機患者も多い――。新型コロナウイルス対策の政府専門家会議メンバーで、日本医師会常任理事の釜萢(かまやち)敏さんは3月、そんな報告を受けて強い危機感を抱いたそうです。どう対処したのか。次の流行に向けた課題は? お話を伺いました。
――新型コロナウイルスの脅威についてどう認識していましたか。
当初、中国で武漢市を封鎖したり新たな病院を作ったりするなどの情報が入り、これは容易ならざる事態だ、と感じました。その後、国内ではクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスで感染者が報告された。クルーズ船には重症になりやすい高齢者も多く乗船していたため、PCR検査の陽性者は全員入院という対応をしました。重症者が多く出たため、関東一円の病院に広域搬送しました。私の地元の群馬の病院にも運ばれました。
現場からの報告を聞くなかで、当時は軽症者が多いという認識でした。
ですが、2月下旬ごろになると、軽症と思っていた人が発症後7日過ぎあたりから急激に悪化する例があると聞きました。呼吸困難が始まるととたんに人工呼吸器をつけないといけないぐらいに酸素飽和度がどんどん下がってしまう、と。「突然症状が悪化する例があって、この病気は非常にやっかいです」という話を聞きました。
――3月30日、日本医師会の定例会見で「緊急事態宣言を出した方がいい」と述べました。なぜでしょうか。
全国の医師会と毎週テレビ会議をしていて、現場の状況が入ってきたからです。3月下旬は特に東京が大変でした。病床を増やしたが、1床空くと直ちに病床が埋まる。さらにかなりの待機があり、重症の人もいると聞きました。もう通常では考えられない事態。医療現場は逼迫(ひっぱく)しており、救える命が救えなくなる可能性もある。そんな強い危機感を持ち、医師会として医療が緊急事態になっていることを言わざるをえませんでした。
――4月1日、「一部地域では病床が不足しつつある」として、日本医師会が「医療危機的状況宣言」を出します。
東京では、医療機関の協力態…