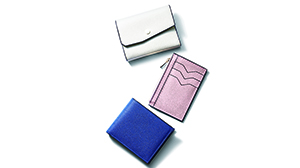漱石が生きた「明治の精神」 大江健三郎さんに聞く
聞き手 編集委員・吉村千彰
100年前の4月20日、朝日新聞紙上で夏目漱石の「こころ」の連載が始まりました。漱石が模索した小説の文体の構築や、考え続けた近代の問題は、現代の日本人にどう響くのでしょうか。ノーベル賞作家の大江健三郎さんが、「時代の精神」という言葉を軸に語ってくれました。
「こころ」を読んだのは高校2年生の時。友人のことを考えていたので、感銘を受けました。次はもう40歳でしたが、先生の遺書の言葉「記憶して下さい。私はこんな風にして生きて来たのです」を引用してエッセーを書きました。
「こころ」は知識人の語りかけの形で、新しい文体を作っています。特別なルビに注意して音読すると東京弁のリズムがあり、生き生きした効果もあげている。時代を感じさせる風格はありますが、今現在の手紙として読めます。
最後の事件を物語った後、さらにスピードと強さを保って、十分に書き終え得るのが作家の実力です。それを「明暗」とともに、よく表現していると思う。
「こころ」はKの自殺で閉じ…