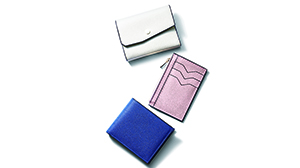「大学改革」が奪った研究の自由 競争が目的化したその先にあるもの
聞き手・田中聡子
国立大学の学費値上げの議論が広がっています。値上げに追い込んでいるものは何か、そのことで失うものとは――。教育学者の古川雄嗣さんに聞きました。
◇
奪われた環境とは
ここ数十年の「大学改革」は、文教政策として「一番やってはいけないこと」をやってきました。大学と研究者を競争に駆り立て、「役に立つ研究」への「選択と集中」を進め、自由で多様な研究と教育ができる環境を奪うことです。
この方向を決定づけたのは、2004年の国立大の独立行政法人化です。独立行政法人とは、いわば国の「代理人」です。国が大学を直接運営するのは非効率だ、運営は代理人にやらせて、国は代理人同士を競争させるべきだという考え方です。
財布のひもをしばった政府
競争に駆り立てるために、政…