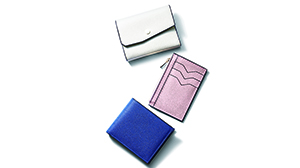「やろうと思ってもできんのや」 感染症広がる避難所、悪化する衛生
「40・3度の熱があるって」
能登半島地震発生から10日目の午前。約100人が避難している石川県輪島市の鳳至(ふげし)公民館がざわついていた。
女性(72)が毛布にくるまり、動けない。救急車で搬送され、新型コロナとインフルエンザに感染していたと診断された。2日後、同じ部屋で寝ていた男性が新型コロナに感染したとわかった。
この公民館では1時間に1度、15分間の換気を徹底している。マスクやアルコール消毒液も用意した。だが断水が続いており、衛生状態を保つのは難しい。毎日のように避難者が救急車で運ばれているという。館長の七浦正一さん(76)は言う。「(感染症対策を)やろうと思ってもできんのや。日々乗り越えるのが精いっぱいだから」
厳しい寒さの中、疲弊する被災者に震災関連死のリスクが高まっている。石川県が発表する災害関連死とみられる死者数には12日だけで新たに6人が加わり、14人になった。
避難所を回って感染症対策の助言をしている防衛医科大の加来浩器教授(感染症疫学)は「すでに感染症が集中的に発生する避難所が増えている。せっかく助かった命を関連死で失わせないため、できる限りの対策が必要だ」。
「毎晩のように救急車」「給水車入れず」
断水や停電が続く能登半島地震の被災地では、避難所の衛生状態が悪化している。地域には高齢者が多く、体調を崩す人も増えている。
石川県能登町の避難所で9日、80代の男性が心肺停止となり、病院に搬送された。男性はその後死亡。町は災害関連死とみられるとしている。自動体外式除細動器(AED)による処置の現場に居合わせた30代の男性は「高齢の避難者は『ひとごとではない』とショックを受けたはず」と話す。
輪島市内の公民館では、高齢…